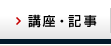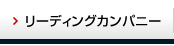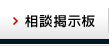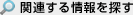パワハラを生産性向上に利用しよう
厚生労働省は1月30日、職場における「パワーハラスメント」の定義を発表した。
この「パワハラ」 と 職場での「指導」の境界は未だ曖昧な部分が多く、人事担当者も
この問題に悩まされる事は多い。
ご存じのとおりパワハラ問題が増加している原因には、以下のような企業を
取り巻く現状がある。
① 境界線(基準)が曖昧なため、社内教育の際にも説明は曖昧になり、
結果、現場に落とし込めない。または誤解を招く。
② 上司の世代(40歳以上)と部下の世代(30代以下)では、暴力(暴言)に
対する許容範囲が大きく異なる為、表面的には理解しても納得はしていない。
③ これからの低成長時代に多くの企業は、売上が下がり続ける。売り上げ
維持のプレッシャーは年々増し、当然部下への要求やノルマもきつくなる。
④ 精神疾患(うつ病)の労災認定は年々増加の一途をたどっている。
⑤ 上司・部下ともにコミュニケーション能力も集団生活の中で他者と妥協
する力も前世代より劣っている。(核家族化・地域コミュニケーションの喪失)
このような現状ゆえ、最近ではパワハラの基準を誤解し、部下を叱れない上司
や「正当な指導」を放棄する上司が出てきている。
言うまでもなく 職場は闘いの場 だ。 厳しいノルマも指導も職場には不可欠だ。
これが「必要ない」というのは、「評論家」であろう。
大切なのは、闘うチームを維持しつつも、企業ブランドを傷つけ、同時に
働く仲間達の自尊心さえ奪う陰湿なハラスメント(嫌がらせ・いじめ行為)を防ぐ事だ。
考えてみてほしい。
上司として尊敬できる者が陰湿ないじめをしたり、暴行をするだろうか。
このような問題が発生するのはそもそも昇格基準や社内風土に大きな欠点
があるはずだ。
根本的解決をせずして、パワハラの基準をいくら従業員に教育しても、
それは「火種を断たない消火活動」で、その後も火は至る所から起こり続け、
確実に企業を蝕んでいくだろう。
では根本的な防止策を講ずる為にはどうすればよいのだろう。
まず考えるべきことは、
好業績のプレイヤーと、優秀なリーダーとでは違う能力が必要という、
いたって基本的な事を改めて人事部が全リーダーに認識させることだ。
リーダーとしての資質が低い者をリーダーにするリスクは、パワハラなどの
トラブル多発だけにとどまらない。人材を枯渇させ、企業の生産性を著しく損なわせる。
しかし現実には、高成績の従業員 をマネージャーに昇格させない事は大変に難しい。
その理由は、
① チームの「成績への動機づけ」に支障が出る。
② 好成績者本人へ「マネージャーに昇格させることができない」と説明することで、
エース級の従業員を失う可能性があり、その結果短期的に売上が減少するリスクを伴う。
③ 上司そのものがリーダーとして資質(人間的魅力など)を備えているか問われる事となる。
この問題の根本的解決の鍵は、やはり基本のとおり人事考課のフィードバック時に
昇格基準を部下に対し明確に伝える事だろう。
●マネージャーに昇格するのは、「過去の業績に対する報酬・評価」ではない事
●マネージャーに昇格する者は、リーダーとしての能力を期待できる者である事
●プレイヤーからマネージャーになる者は、リーダーへの「自己変革」ができる者に限られる事
●マネージャーには、周りからの支持があるかないかが問われる事
●マネージャーには、部下・他部署・経営への共感的理解が必要な事
などの基本的な昇格基準を全ての上司が必ず部下に伝える様に「考課表」に工夫をするなど、
人事考課のフィードバック時の基本的説明の「再現性」を追求するしかない。
また、
「成績3位でリーダーとしての資質の高い者はマネージャーへ昇格する可能性があるが、
成績1位でもリーダーとしての資質が低い者がマネージャーに昇格する可能性はゼロだ。」
などと 誰でも話せて、誰が聞いても誤解が無い ような、「簡単で分かりやすい」フレーズを
人事部が用意して必ず伝える仕組みとするのも有効だ。
この時、成績は1位だがリーダーとしては問題がある社員に対し、「何が足りないか」指導する
いいきっかけになる。
信頼に値する人間性を持ったリーダーさえいれば、「パワハラの法的境界線」などに神経を
とがらせなくても、そもそも問題は発生しないはずだ。
パワハラと指導の境界線は、下記の判例のように裁判所さえその判断は二転三転し、
判断に苦慮している。
(例) 前田道路事件―高松高判平成21年4月23日労判990号134頁
しかし、人事部は、このような曖昧な法的境界線などに囚われること無く、この問題の
根本的な原因とその影響を巨視的に見極め、パワハラ防止を単なるリスク管理教育に留めず、
「昇格基準の変更」や「リーダーシップ教育」を実施して、
「パワハラ問題の根本的解決」と同時に「人間的魅力のあるリーダーの育成」を目標に取り組めば、
このネガティブな課題も面白味のあるダイナミックな施策になるのではないだろうか。
ちょうど「パワハラの定義」が注目されている時だ。これをチャンスに「リスク管理」という体で、
「生産性向上」・「企業文化の変革」までを目標に「パワハラ防止」に取り組んではいかがだろうか。
|
|
株式会社Human&Society 代表取締役 |
|---|---|
|
労働問題を企業人事で活かすことのできる日本でも数少ない労務人事の専門家。
従業員30,000人規模の企業の人事部長を務めた人事のプロ。 1,000件を超える労働問題・訴訟・外部労働組合との団体交渉、100件を超える労働基準行政対応などを責任者として直接対応し、企業負担を最小限に抑え解決に導いた実績を持つ。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)