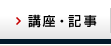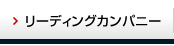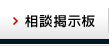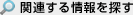パワハラ事案発生後の再発防止策について
~パワハラ行為者は変われるのか~ パワハラ事案発生後の再発防止策について
パワハラ事案が生じた後の再発防止策について、何か有効な手立てはないかと、ご相談を受けることがあります。
厚労省の指針では、パワハラの相談があった場合の事後の対応として、再発防止に向けて周知・啓発、研修等の措置を講ずることと
なっていますので、多くの企業では、そうした対応をすでに取られていることが多いと思います。
にもかかわらず、実際に行為者とされた方々からは、
「結局、何が問題だったのか分からない」
「パワハラ研修も受けていたので気を付けていたつもり。でも、訴えられてしまった」
「自分に問題があったことは分かった。でも具体的にどうすれば良いのか分からない」
等という戸惑いの声を伺うことがあります。
また、行為者とされた方の中には、納得感が持てないまま、会社側に対して対立姿勢で臨む方や、事案後、仕事へのモチベーションが
低下したり、自身のキャリアに疑問を持ち等その結果、パフォーマンスが低下する方も見受けられます。
こうしたケースに共通する要因として、行為者それぞれの課題に応じた研修ではなく、画一的な研修の実施にとどまっていることが考えられます。
では具体的にどのような対応が考えられるでしょうか。
ハラスメント予防には「意識」「知識」「スキル」の3要素が必要であると考えます。
一つ目の「意識」は、部下への人権配慮の視点や自身の責任や影響力等、ハラスメント予防に対する本質的な理解ができているかどうか
という点です。
二つ目の「知識」は、ハラスメントに関する基本的な知識を指します。
最後の「スキル」に関しては、感情のマネジメントや部下との関係構築等といった職場でのコミュニケーションスキルを指します。
予防のためには、ハラスメントの定義や類型など基本的な情報(「知識」)を知っておくことが前提になります。また、その知識を実践で活用
するには、一定のコミュニケーションスキルが必要になります。
そのため、行為者とされた方々に対して、知識の再確認のための研修や、部下指導の幅を拡げたり、声掛けのバリエーションを増やすための
スキルトレーニングを行うことを第一に検討される人事も多いかもしれません。
一方で、行為者とされる方の中には「これまで一生懸命に部下を教育してきたつもり。指摘すること、注意することすらハラスメントといわれて
しまっては、どう関われば良いのか分からないし、正直、部下と関わるのが怖い。」とお話になる方も多く、こうした戸惑いはハラスメント予防に
関する本質的な理解(「意識」)が十分にできていないことから生じるものと思われます。
このようなケースの場合は、意識のアップデートが行われない限り、幾ら知識やスキルを詰め込んでも、効果的な行動改善にはつながりにくいと
考えます。
再発防止のためには、行為者とされた方が、何に戸惑われているのか、指摘されたことについてどの程度理解し、納得できているのか等を丁寧に
聞き取り、上記の3要素のどの点に課題があるのか確認をしたうえで、必要なトレーニングを実施することが有効です。
(コラボレーター 伊東 あづさ)
|
|
キューブ・インテグレーション株式会社 シニアコラボレーター |
|---|---|
|
公認心理師/臨床心理士/キャリアコンサルタント
【専門領域】産業精神保健、復職支援、認知行動療法、コーチング 外食企業にてマネジメントを経験後、飲食店不振店再生プロジェクト等に携わる。その後大手コーチングファームにて、管理職層のリーダーシップ開発等を目的としたコーチング、研修講師等を担当する。現職では、メンタル不調者への面談や復職支援等を担当。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)