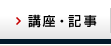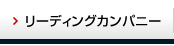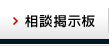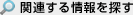精神科の受診や治療に難色を示す社員への関わり方(1)
勤怠不良が断続的に続き、その背景にメンタル不調があることを、
本人も薄々理解しながらも、専門医療機関受診に抵抗を強く示すケースを、
企業の臨床場面でよく経験します。
また、人事担当者からも、そのような相談を受けます。
人事としては、安全配慮上、休職発令したいところですが、
本人から休職診断書が提出されないと、
なかなか休職の手続きを進めにくい事情もあり、
どのように対応したらよいか困ってしまうわけです。
昨今、メンタル疾患は、誰でもなり得る病であるという啓発活動により、
一昔前よりも精神科受診へのハードルは大分下がったように思います。
とはいえ、
“精神科を受診すると、何か一線を越えてしまうのではないか”という思いを
強く持っている人が少なからずいるのも事実です。
しかし、メンタル不調により、勤怠や業務に支障を来たしている場合、
未治療のままでいると症状が更に進行するリスクが高いため、
できるだけ早急に専門医へつなぐことが肝要です。
精神科の受診や治療に抵抗を示す背景には、様々な不安が介在していますが、
私が臨床場面でクライエントから聞く不安感情は、主に次のようなものがあります。
1.メンタル疾患の診断に対する不安
2.薬物治療に対する不安
3.休職に対する不安
1の場合は、“自分はメンタル疾患ではない”という態度(否認)で
表現されることも多くあります。
2を抱えている場合、社内外の専門家の力を借りて、
薬物療法のあらましについて説明する必要があります。
3の場合は、休職中の収入はどうなるのか、自分の担当業務は大丈夫か、
家族に心配や迷惑を掛けてしまうのではないか、
復帰できなくなるのではないかといった様々な気持ちが混在していることが多いです。
では、こういった不安を訴える従業員に対し、どのように対応したら良いのでしょうか。
次回は、その詳細について述べていきます。
|
|
キューブ・インテグレーション株式会社 エグゼクティブコラボレータ― |
|---|---|
|
公認心理師/臨床心理士/精神保健福祉士/社会福祉士/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
2009年度日本うつ病学会奨励賞受賞 精神科クリニック、障害者職業総合センター等で集団精神療法、デイケア、就労支援の他、スクールカウンセラー、千葉県医療技術大学校非常勤講師、千葉県庁健康管理室相談員を歴任。その後、EAP事業会社にて復職支援を中心にメンタルヘルス対策支援に従事。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)