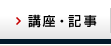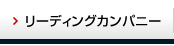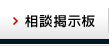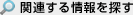部下育成の黄金比定説“褒める3、叱る1”は本当に良い?
【Q】
部下を潰さないように、褒めたり認めたりするのが大切、ということはよく聞きます。しかし、そうすればするほど結局部下のストレス耐性は弱くなってしまっているのでは?と悩む時があります。
たとえば、褒め続けている間は良いのですが、褒められなくなったら、余計に不安感がつのったり、自信がなくなるのではないか?と。
やはり真っ白な新入社員ほど、最初から厳しく接していく方が、総じて強い社員に育つのでしょうか?
“褒める3、叱る1”という定説は、長期的に見ても正しいのでしょうか?
【A】
上司がアクセルとブレーキの二元論にハマっていると、こういう理屈になります。
たとえば・・・
・ユーモアで笑わせてリラックスを誘う
・士気を鼓舞するような話し方を工夫する
・存在を認めながら行為を叱る
・時には部下に教えてもらう場面を作る
・別の人を怒る姿を見せてメッセージを伝える
・禁止をすることでやる気を出させる
・セールスのテクニック(パソナ、アイドマなど)を使って行動を喚起する
など、褒める・叱る以外の選択肢は無数にあります。
また、部下は上司を見て育ちます。
上司が「褒める」「叱る」の二元論にハマっていると、部下も「褒められるか?」「叱られるか?」に意識がいきます。
上司としての柔軟性を高めるために、たとえば“指揮者”を研究してみてください。
・厳格に正しさを表現する、怖い顔をした指揮者
・完全に全体をコントロールしたい指揮者
・ほとんど何もしないで笑っていて、要所で軽く指示をする指揮者
・自分自身が音楽を楽しんで、ダンスをするように指揮をする指揮者
など、人を従わせる方法にはたくさんのバリエーションがあります。
それでも、「褒める」「叱る」の二元論の範囲内でお答えするならば、“存在”や“信念(考え方)”を褒め、“行動”を叱るのが良いと思います。
「お前のことは大好きだけれど、あのやり方はちょっと良くないな」とか、
「考え方は素晴らしいけれど、あの行動はね」という感じです。
“褒める3、叱る1”の定説と呼ばれている件については、3回とか1回という回数を数えるような考え方は、人間に対する
アプローチとして礼を欠いていると思います。
相手はそれを察知します。
|
|
株式会社fUTSU Lab. 取締役所長 |
|---|---|
|
不登校・うつ病・失業などで悩む人たちが心の問題を解決して、実際に学校に通ったり仕事に復帰するためのサポートをしています。 重度のうつを発症し10年近い療養生活を送る。自らの自殺未遂の後、闘病仲間の自殺を機に、独力で社会復帰。以来、自らの経験を元に、様々な心理学・心理療法を学び、3,000名を超える心理カウンセリングを行う。生きるための心理学の伝道師として活動。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)