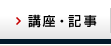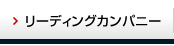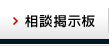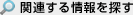知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題
企業における大きなリスクのひとつが「ハラスメント」と「メンタルヘルス不調」です。
一見すると別々の問題のように見えますが、実は両者は密接に結びついています。
ハラスメントが原因で心を病む社員がいる一方で、上司や同僚のストレスやメンタル不調がハラスメントを引き起こす要因となることも少なくありません。
つまり、ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題なのです。
今回は、人事総務担当者の皆様に向けて、この2つを切り離さずに対策を行うことの重要性と、研修導入の必要性についてお伝えします。
●ハラスメント防止研修の「限界」
多くの企業ではすでにハラスメント防止研修を実施しています。
「パワハラ・セクハラ・マタハラの定義を学ぶ」
「やってはいけない行為を理解する」といった内容は欠かせません。
しかし実際には、研修を受けても職場の雰囲気や人間関係が大きく改善しないと悩む企業が少なくないのが現状です。
一体なぜ、効果が限定的なのでしょうか。
一つは、知識偏重の研修になりやすいことです。
法律用語や定義を理解しても、日常のコミュニケーション場面で「この言い方はハラスメントになるのか?」「部下を厳しく指導する時にどう配慮すべきか?」という具体的な疑問には答えられないままになってしまいます。
もう一つは、上司自身の余裕のなさです。
プレッシャーや多忙さからストレスを抱え、気持ちに余裕がなくなると、知らず知らずのうちに強い言葉が出てしまうことがあります。
つまり、役職者のメンタル不調がハラスメントの温床になるのです。
●メンタルヘルス対策の「盲点」
一方で、多くの企業はメンタルヘルス研修にも力を入れています。
セルフケアやラインケアを学ぶことで、社員が心身の不調に早めに気づき、適切に対応できるようにする取り組みです。
しかし、この研修も単独では限界があります。
「自分のストレスに気づきましょう」と学んでも、実際の職場で上司から理不尽な叱責やハラスメントを受けている場合、セルフケアだけでは対処しきれません。
また、部下を支える立場にある役職者自身がストレスを抱え込んでいると、周囲の社員にまで悪影響が広がります。
つまり、ハラスメントとメンタルヘルスを別々に扱うこと自体が限界を生んでいるのです。
●表裏一体で捉えることで見えてくる解決策
では、どうすればよいのでしょうか。
答えはシンプルです。
ハラスメントとメンタルヘルスを「一体のテーマ」として研修すること。
たとえば次のようなアプローチが効果的です。
・役職者自身がストレスを整える「セルフケア力」を高める
・部下との信頼関係を築く具体的な方法を学ぶ
・「これはハラスメント?」「これは指導?」と迷いやすい場面を事例で検討する
・ハラスメント発生時の対応フローを理解する
こうした学びを一度に取り入れることで、単なる知識の習得にとどまらず、「できる」スキルとして職場で実践できるようになります。
●新任役職者こそ早期に学ぶべき理由
特に新任役職者にとって、この研修は大きな意味を持ちます。
昇進直後は「指導する立場になった責任感」と「経験不足からくる不安」が入り混じる時期です。
その結果、強すぎる言葉で叱責してしまったり、逆に過剰に萎縮して適切な指導ができなかったりと、アンバランスな対応に陥りがちです。
この段階で「ハラスメントとメンタルヘルスの関係性」を体系的に学んでおくことで、早期から健全なリーダーシップを身につけることができます。
これは、企業全体の心理的安全性を守るための投資ともいえるでしょう。
なお弊社のハラスメント×メンタルヘルス研修の一般的なプログラム例を紹介しますので、必要に応じて参考にしてみてください。
|
|
株式会社マイルートプラス代表取締役 |
|---|---|
|
社員が自力でメンタルを立て直せる力を身につける研修・講演会プログラム 「若手社員の休職・離職」「管理職のメンタル不調」「自律社員の育成」「カスハラ・クレーム対策」「パワハラ対策」…これらすべて、7,000名以上のお客様をサポートする中で導き出した自力でメンタルを立て直す3ステップで解決できます。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)