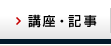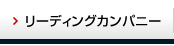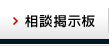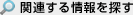新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ
企業において「ハラスメント対策」と「メンタルヘルス対策」は切っても切れないテーマです。
特に役職者にとっては、部下の成長を支えると同時に、自身も健やかなメンタルを保ちながらリーダーシップを発揮することが求められます。
しかし現場では、
「ハラスメントをしてはいけないのは分かっているけれど、どこまでが指導でどこからがハラスメントになるのか分からない」
「自分自身のストレス管理ができていないため、余裕をもって部下に接するのが難しい」
といった声が多く聞かれます。
弊社では新任役職者向けにハラスメント&メンタルヘルス研修を実施していますが、この研修も企業の人事総務担当者の方々とお話する中で生まれたものです。
今回のコラムでは、なぜ今、役職者にハラスメントとメンタルヘルスの研修が必要なのかを独自の視点で解説します。
●なぜ今、役職者にこの研修が必要なのか
近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。
・働き方の多様化によるコミュニケーションの複雑化
・ハラスメントに対する社会的な注目度の高まり
・心の不調を抱える社員の増加
こうした背景のなか、役職者には「ハラスメント防止の担い手」であると同時に「部下の心を守る存在」であることが強く求められています。
ところが、多くの新任役職者は管理職としての経験が浅く、ハラスメントの線引きや、部下と信頼関係を築く方法、さらには自分自身のストレスマネジメントのスキルを学ぶ機会が十分ではありません。
多くの企業ではすでにハラスメント研修を導入しています。
しかしその一方で
「研修を実施しているのに現場での改善が進まない」
「受講直後は意識が高まるが、日常の業務に戻ると効果が薄れてしまう」
といった悩みも少なくありません。
では、なぜ十分な効果が得られないのでしょうか。主な理由は次の通りです。
1. 専門用語ばかりで実務に活かせない
多くの研修では、ハラスメントの定義や法律上の区分、ガイドラインといった“知識”が中心になります。
確かに必要な情報ではありますが、専門用語が多すぎて受講者の理解が追いつかず、結果として「分かったつもり」になってしまうケースが目立ちます。
役職者が現場で本当に必要なのは、知識そのものよりも「具体的にどう行動すればいいか」という指針です。
2. 受講者が「他人事」になりやすい
一般的な研修では、事例紹介や法的な説明が中心となるため、「知識としては理解したけれど、自分の現場にどう当てはめればいいか分からない」という声が多く聞かれます。
特に新任役職者は「まだ自分は大丈夫だろう」と思いがちで、学びが行動変容に結びつきにくいのです。
3. メンタルヘルスとの関係性が見落とされている
ハラスメントの背景には、上司側のストレスや余裕のなさが大きく影響しています。
しかし、多くの研修は「やってはいけない行為」の理解に留まり、「なぜそれが起きるのか」「どうすれば未然に防げるのか」まで踏み込んでいません。
メンタルヘルスの視点が欠けているため、再発防止策として不十分になりがちです。
弊社で実施する研修は、知識の詰め込み型ではなく「実践できるスキル」を中心に学べること、そして 役職者自身のメンタルを整えることと部下との信頼関係づくりを両輪で扱うことを重視しています。
そもそも弊社が自分で自分のメンタルを立て直す3ステップを開発し、7,000名以上のお客様のサポートをしてきた経験があるからこそ、単に知識や専門用語の学習にとどまらない、実務的な研修が実施できるのです。
「知っている」から「できる」へ。
これこそが、多くの企業が求めながらも既存研修では実現しにくかった点なのです。
弊社のハラスメント×メンタルヘルス研修の一般的なプログラム例を紹介しますので、必要に応じて参考にしてみてください。
|
|
株式会社マイルートプラス代表取締役 |
|---|---|
|
社員が自力でメンタルを立て直せる力を身につける研修・講演会プログラム 「若手社員の休職・離職」「管理職のメンタル不調」「自律社員の育成」「カスハラ・クレーム対策」「パワハラ対策」…これらすべて、7,000名以上のお客様をサポートする中で導き出した自力でメンタルを立て直す3ステップで解決できます。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)