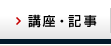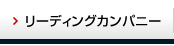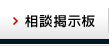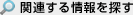若手社員の成長を健康管理の面から考える
企業の方から、若手社員が仕事中うとうと(ぼーっと)している、集中力がない、体調不調での休暇取得が多い、などの理由でなかなか仕事を任せることができず、結果として若手社員の成長につながりにくいという話を伺うことがよくあります。
こういった社員は“やる気がない社員”と思われがちですが、実は“やる気”ではなく、生活習慣の乱れが原因となっていることも多く、そういった社員が体調管理に関心を持ち、スキルを身に付けることで改善につながることも多くあります。
若手社員が体調管理をおろそかにしてしまう原因として、以下のようなことがあります。
・ 『食事はバランスよく食べましょう』と言われても、“バランスがいい”とはどういうことかわからない。自炊は苦手。食事は“お腹が満たされればいい”と考えている。
・ 夜遅くまで動画を見たり、友人等とコミュニケションを取ったりすることで、睡眠の質が低下したり、十分な時間を取れなかったりする。
・ 社会人になり運動をする時間が取れなくなった。
・ 学生から社会人への切り替えが出来ていない(特に初めての一人暮らしの場合、環境の変化が大きく、順応できていない)。
・ 健康への課題認識が乏しいため、健診結果で有所見があっても放置してしまう。
体調管理をおろそかにしてしまうことで、自覚症状のないままじわりじわりと生活習慣病が進行してしまい、若手社員であっても健康診断で異常値が出ていることもあります。
その状態を放置すると、生活習慣を改善するきっかけを得られないまま、ずるずるとパフォーマンスが低下し、ますます仕事への意欲がなくなってしまう、という悪循環に陥ってしまうことにもなります。
企業によっては新入社員の健康教育の一環として集団研修を実施しているケースもありますが、集団研修は一人一人のレベルに応じた内容にすることが難しいため、体調管理に無関心な方は、研修を受けても自分事として捉えられず、改善につながらないケースが見受けられます。
企業側も、プライベートな部分である生活面について踏み込んだ対応をすることに躊躇してしまったり、長期的なサポートをする人材の確保が難しく、個別対応に限界があったりすることもあるでしょう。
理想としては、若手社員の体調管理について、まず改善の必要があるのかどうかを判断するところから、実際の改善指導、そしてそれが定着するまで、健康管理に関して専門知識を持った人材がサポートを行うことが望ましいと考えます。
もし、自社内にそのような人材がいない場合は外部の専門家を活用するのも一つの方法です。
仕事において基本となるのは、個人が自身で体調管理を行うことであることは言うまでもありませんが、若手社員の成長を考える上で、企業としてもう一歩踏み込んで取り組んでみてはいかがでしょうか。
(シニアコラボレーター 田口 朋子)
|
|
キューブ・インテグレーション株式会社 シニアコラボレーター |
|---|---|
|
保健師
【専門領域】産業保健 病棟看護師や教職に従事した後、保健師として特定保健指導受託企業に転職。現在は産業保健師として企業の健康経営と社員の健康管理支援を行っている。 |
|
専門家コラムナンバー
- 合理的配慮とハラスメント〜その線引きと職場に求められる対応 (2025-09-30)
- 部下に強く言えない人に欠けている自信とは?原因と改善策 (2025-09-28)
- 育児と仕事の両立支援 (2025-09-26)
- 知ってる?ハラスメントとメンタルヘルスは表裏一体の課題 (2025-09-24)
- 新任役職者に必須!ハラスメントとメンタルヘルスを同時に学ぶ (2025-09-21)